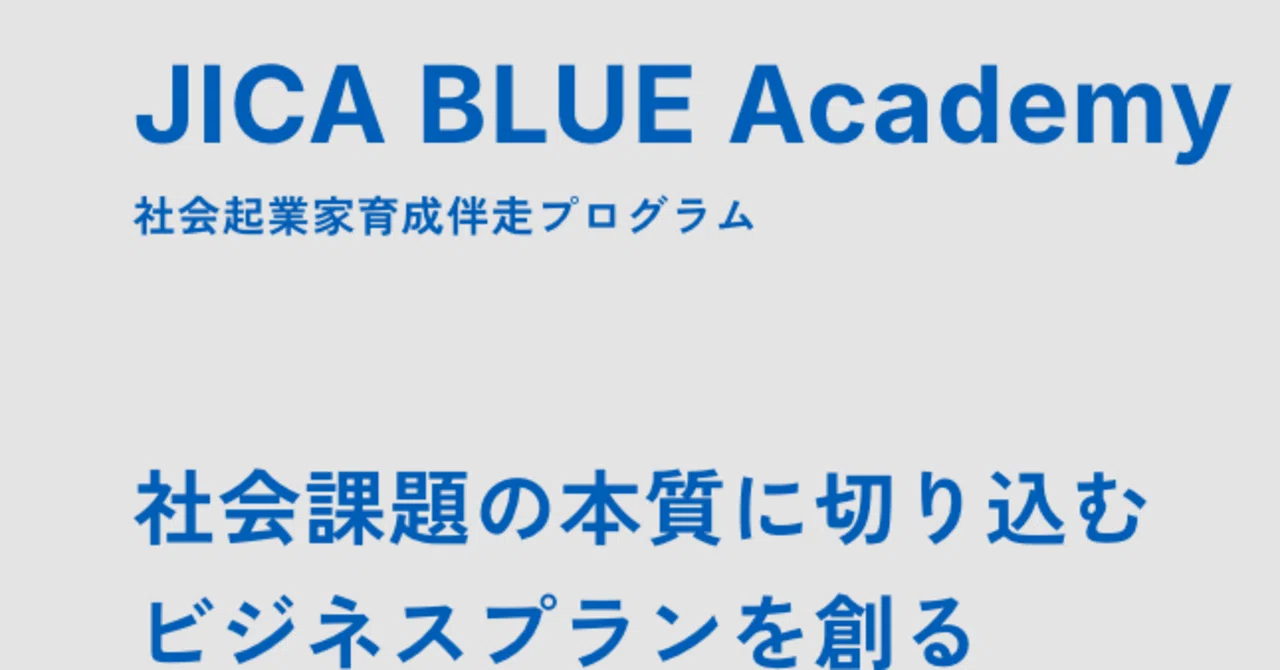8月下旬の最終面接で、志望動機や自分がやりたいことを話します。その整理とアウトプット兼ねて記事にしてみました。
横目で見るのはやめたい
青年海外協力隊が帰国した後の活動である社会還元を、JICAと青年海外協力隊OV会では力を入れています。
2年間、途上国で培った経験と知識をただ、良い思い出として残すのではなく、実践として日本社会、または途上国に還元しよう、という流れです。
そのひとつに、社会起業家による、ビジネスで社会課題を解決しようという流れがあります。国際協力やソーシャルビジネスで有名な企業は、ボーダレス・ジャパンさんが最初に脳裏をよぎるのではないでしょうか。
このボーダレス・ジャパンさんのすごいところは、培ったノウハウを研修で1,000人以上の人にお伝えしていることです。
このプロジェクトが、JICAと提携し、協力隊OVも受けられることになりました。
今年が2回目のため、2期生の募集がありました。
今までであれば、「帰国したての若い人たちがいけばいい」と横目でみていたのですが、知り合いが1期生で受講していたこともあり、自分としては興味津々でした。
私が25歳で協力隊に応募した時の理由は、「今のままぬるま湯につかっていたら、自分の人生に未来がない」という危機感がありました。
43歳の今、その危機感がどことなくありました。
いや、帰国して13年、危機感がありながらも蓋をしてきた自分がいました。
2024年に宮崎OV会の会長職を拝命したことをきっかけに、2024年1次隊の派遣隊員と現在でもやりとりしています。
「頑張れよ!!」という上目線ではなく、途上国と宮崎のそれぞれのフィールドで、ライバルのように高め合っていたいと想うようになっていました。
だから、年齢とか地域とか関係なしに、挑戦しようと考えました。
どちらかというと、傍観者でこのまま年を取ることだけは嫌だったというのが根底にあります。
結果、応募して書類選考が通過。8月下旬に最終面接を受けてきます。
1期生の何かの情報でみたのですが、倍率が3倍以上あったような気がしています。まさに、協力隊と同じ倍率ですよね。気負わずボチボチ受けてきます。
2回目のKTCのような感じ
協力隊で良かったなーと思うことは、途上国で2年間ボランティアすることだけではありません。「青年海外協力隊」という文脈で出会える人が財産です。
例えば、訓練所。駒ヶ根訓練所であれば、KTC。二本松訓練所であれば、NTC。この出発前の3ヶ月間を訓練所で過ごすことって、協力隊ならではと思います。なぜなら、世界中、海外ボランティアする人ってのは意外といるからです。2年間の海外生活以上に、活動しているNPO団体もあることに気がつきました。
そう考えると、海外ボランティア・国際協力っていうジャンルで行くと、何が協力隊を差別化しているのか。
ここを言語化すると、「訓練所」にあると思います。あの訓練所での生活というのは、すごく心と身体に残る何かがあります。
前置きが長くなりましたが、私は、このJICA BLUE Academyを”第二の訓練所”と位置づけました。二度目のKTCと仮想して、望むことにしたのです。
なんか楽しそうで。
起業って何をするのか?
私は、経理代行を本業にしています。
医療福祉・飲食店・ソフトウェア会社など、常駐しないのですがネット上で常駐しているフルリモートで、経理を行っています。
昨今は、経理担当者が退職するリスクや社内雇用を減らしたい企業が増えてきているので伸びている市場です。
そのような本業で培った知識と技術を、協力隊出身者の起業家に提供するサービスを始めます。
起業家には、社会課題を解決したい強い想いがあります。
でも、人・モノ・お金がかなり限られています。
そのような立ち上げ期に、無料で支援するサービスがあり、かつ、経理などをしなくても、自分にしか行えない本業に専念できる環境があれば、より起業家が経営を継続できると思うからです。
1年で30%、3年で10%が起業家の生存率です。(中小企業白書などより)
実績を出しながら自分の活動をアウトプットする
今後の流れは、
1・2年で無料で支援してきて起業家がどのよな経営状態になっているか、その実績を積み上げます。
3〜5年で、「私もサポートしたい」という人が手を上げてくれる仕組みをつくります。例えば、WEBデザイナー、士業など、起業に必要なスキルをもっている協力隊出身は大勢います。また、産休・育休中の女性など、「スキマ時間を活用して、お手伝いしたい」などの潜在ニーズもあると思います。そして、3年から7年くらいで、事業承継の支援実績を1社つくります。
NPO800社のアンケートでは、800社中200社(約25%)が後継者不足の経営課題を抱えています。
・高齢化のため、事業承継をしたい
・準備が進まないのは、適切な後継者がいないから
NPOサポートセンター、NPOの代表810名に聞いた「NPO代表者白書」を発表 特定非営利活動法人NPOサポートセンターのプレスリリース(2025年4月7日 10時00分)NPOサポートセンター、NPO prtimes.jp
OVの先輩たちに多くの経営者がします。
後継者が候補としれあれば、まったく問題ありませんが、後継者探しは重要な課題に思います。
それに対して、JICA BLUE Academyが開催されるということは、それだけ社会的なニーズ、帰国後の協力隊の進路に「起業」があるからです。
これらをマッチングさせることができれば、双方にとって良いかと思います。ただ、理想を掲げますが、事業承継というのはかなり大変です。私は仕事柄5社の事業承継やM&Aの経験がありますが、言葉以上に大変な思いをしました。取引先・従業員・株主・銀行・税理士・弁護士・売り手・買い手など、多くの関係者を巻き込んだプロジェクトになるからです。
だからこそ、取り組むことの意義や達成感も尋常ではありませんでした。
そんな遠くない未来の話になりますが、事業承継を「協力隊OV」という文脈で考えた時に、多少のニーズがあると思います。多くの方は、自社の地域で解決しますが、一部の人には、想いを含めて「協力隊」に承継してもらいたいと思っているのではないでしょうか。
国際協力≠青年海外協力隊、ではないと思った
宮崎県のOV会をやっていて思ったことは、協力隊=国際協力に強い関心がある、ということは成立しないということです。
理由は、宮崎県で行われる国際協力イベントに、青年海外協力隊出身者の参加率が思った以上に高くないからでした。
それとは逆に、国際協力イベントではないのですが、
「協力隊OVがやっているイベントだから手伝いにきました」という声を聞いた時にふと思ったのが、「国際協力≠青年海外協力隊」でした。
青年海外協力隊出身者の人は、国際協力も好きではあると思いますが、それ以上に、青年海外協力隊、が好きなのです。
そういえば、私がその一人です。
バヌアツの貧困や教育問題は気になりますが、そこへの情熱ややる気スイッチはイマイチあがりません。
でも、青年海外協力隊のOV会などについては、情熱ややる気スイッチが一気にあがりました。
理由はないんですよね。ただ、好きなんだと思います。
だから、特定の国の社会課題を解決したい、という強い思いがないので、ソーシャルビジネスは向いてないなと長らく思っていました。
でも、ここ数年、ソーシャルビジネスという言葉が浸透してきて、協力隊起業家が続々と現れる中、経理・バックオフィスサポートということであれば、自分が横断的(複数社の起業家)に支援できると思ったのです。
特にOV会で活動していると、人的リソースが溢れていることに気がついたのです。
週末や特定の時期に、自分の技術や経験を提供したいOV、って一定の割合でいました。しかもその技術や経験って、かなり貴重かつ高価なもの。
でも、OVの皆は「無料でいい」と言います。
この、帰国した青年海外協力隊の人的資源って、今以上に活用する機会ってつくれるような気がしたんです。
それを検証するために、まず自分がお役に立てることを実績にしたいと思い、活動をはじめることにしました。
この挑戦の記録は、またnoteでお伝えします。
興味がある方は一緒に考えましょう。コメントお待ちしています!