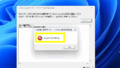DX化についてDとXでわけて考えてみた。わかっているようでわからないDX
DX化やIT化・デジタライゼーション・AIなど、様々な用語が飛び交う昨今。
なんとなく、「便利になるんだろうな」と思いつつも、その違いについてはスルーしてしまいます。
ITエンジニアとして、色々な企業のデジタル化や業務効率をサポートする中、「DXしたい」という要望と「DXします」というサービスの現状に、大きな言葉の壁を感じていました。
今回、税理士の神佐真由美さんのメルマガが自分の大きな悩みのヒントをいただいたので、その本文をきっかけにDXについて考えてきたいと思います。
こちらの記事です。https://mail.os7.biz/b/JaJ8/1908855
DとXをわける
まず、言葉の定義から考えていきましょう。
Dとは、デジタルまたはデジタライゼーションのDです。
今まで手書き伝票だったり、タイムカードを差し込んで印字していたものを、デジタルデータに代えて、ワンクリックで集計するなどです。
Xとは、トランスフォーメーションのXです。
英語では、Transformationと書くのですが、TransをX、と置き換えることが多いため、TではなくXを選択しています。
これは、改革を意味します。私が思う改革の定義は、いままで行っていたことを51%以上変えることを指します。それに対して改善は、5%・10%の業務を変えることを指します。
どちらが優れているかなどが大事ではなく、企業ごとの状況に応じて必要なことを必要なタイミングで行うことが大事です。
Dには2種類ある
デジタル化
Dは2つの段階があると思っています。
1つ目はデジタル化、上述したタイムカードについてです。
例えば製造業で、工員さんが毎日出退勤するたびに、タイムレコーダーにタイムカードを差し込んで印字しているとします。
月末になると、経理担当者がタイムカードをまとめて集計作業をします。
間違えがあれば、本人に確認して修正。
そして、集計が終わり、銀行振込の手続きをする、という流れがあるとします。
1 タイムカードを差し込んで印字
2 タイムカードを集計
3 修正
4 銀行振込
この流れをデジタル化する場合、タイムレコーダーとタイムカードを撤廃し、ipadなどのタブレットを更衣室におきます。
出退勤時は、自分の名前を押します。
月末に、経理担当者が自分のパソコンから集計ボタンを押します。
出退勤ボタンの押し忘れなどがないか確認し、あれば修正。
その後、銀行振込です。
1 タブレットに出退勤を押す
2 タイムカードを集計
3 修正
4 銀行振込
これだけを箇条書きにすると、4工数はほぼ変わりません。
目に見えない部分が変わっているのです。
デジタル化することで、タイムカードという紙が無くなったことがおわかりになると思います。
また、タイムカードから集計をしていた経理担当者の手間がなくなります。
私は、この経理担当者が紙からパソコンに手入力をしていた手間がなくなることがデジタル化の大きな恩恵だと思いました。
なぜなら、私がこの集計作業をしているときは、実に見落としなどがありミスが多発していたからです。私の能力にも問題はありますが、人間がやることにはミスがつきまとうからです。
究極、出退勤に間違えさえなければ、給与ソフトが間違えなく確実に集計します。
これらに気づいてから、私はいかに手入力など自分の作業が介在しないようにするための、一連の流れを工夫しました。
結果、工員さんの出退勤を毎週リーダーがチェックすることで、修正を行ってもらい、集計時にはボタンを押すだけに成功し、銀行振込も数クリックで完了する流れを作れました。
これが1つ目のDである、デジタル化です。
デジタライゼーション
2つ目のDは、デジタライゼーションです。
デジタライゼーションとは、デジタル化したデータをもとに業務改善に活かすことです。おそらく、日本のDXと呼ばれることの9割がここのことを指しているかと思います。私自身、DXとはこのことだと思いながらも、ずっとモヤモヤしていました。なぜなら、DXをうたうSaaS企業の売り文句が、業務改善などだからです。
引き続き製造業の例えから考えていきましょう。
工員さんの勤務時間をデジタル化することで、簡単に給与振り込みができるようになりました。いままでタイムカードから給与ソフトへの手入力から解放されて、経理担当者も少し余裕がでてきました。
次に考えるのは、シフト調整です。
例えば、パート契約の方が月曜日が多く、金曜日が少ないとします。
それらを最適化したい場合、どのような組み合わせがいいか、給与ソフトが自動で提案してくれます。
一昔前まで、ガントチャートのような手書きのシフト表を更衣室に貼ってありました。それらは経理担当者がウンウンうなりながら考えて作っていましたが、いまはソフトがパッと作ってくれます。
そして、製造業であれば工程管理と呼ばれるものがあります。
A製品、B製品ごとに工程があり、材料などの投下タイミングや、人の手が必要なタイミングなど、があります。
それらも現在は、機械ごとにデータ管理をしてい、かつ本部で把握できるようになっています。
そのため、月の受注量によって、工員さんの出勤時間の調整が必要となってきます。
「今月は受注量が少ないから、パートさんの出勤時間を抑えさせてもらい、繁忙期で調整をかけさせてもらおう」
「◯◯さんと△△さんは、130万円の扶養の範囲で働きたい方だから、今月の仕事量はここまでだな」
など、ひとりひとりの働き方を設定すれば、調整が可能です。
デジタル化された出勤簿とデジタル化された工程管理を組み合わせて、最適化をはかることをデジタライゼーションと定義します。
Dによって得られたことは
DXのDについてですが、これをするだけで、経理担当者の業務量は激減し、かつ、売上と人件費の最適化ができるようになったことで、会社の利益は増加します。これぞまさにDXの恩恵といえるでしょう。
では、肝心のXであるトランスフォーメーションである改革の方はどうなんでしょうか?上述は、あくまでもDだけであって、デジタライゼーションしたにすぎません。デジタライゼーションは、業務効率化といえど、会社の業務改善を行っているにすぎません。通常、デジタライゼーションの業務改善であれば、よくて30%の改善です。
改革といえるのは、51%の業務を改善した場合を定義しています。
そのため、トランスフォーメーションの改革をしたいのが経営者の方のお望みかと思いますし、私も改革をしたいと思っています。
しかし、簡単にいかないのがDXのXです。
このXであるトランスフォーメーションをするために、徹底的にDのデジタル化をすることが、大事だと思っています。
Xをイメージしてみる
改革、トランスフォーメーションという言葉があり、会社のビジネスモデルや仕事が51%改革されること、具体的にイメージつくでしょうか?
現時点で、色々な憶測やイメージが社会でありますけど、私は中々イメージがついていないのが現状です。
きっとITにかかわる人たちも、常にどのような未来が実現できるかを考えながら、現状との未来を行き来しながら、試行錯誤していることと思います。私なりにイメージを2つ考えてみたいと思います。
トランプ政権の関税対策を自動で考えてくれる
例えば、2025年7月14日の今日現在、トランプ大統領が関税をアップすることで、日本経済のダメージが懸念されます。
これを中小企業のデジタルと組み合わせることでどのような改革が起きるでしょうか?
1 主要取引先からの受注が激減するため、資金繰り対策とパートさんの勤務時間を減らさなければいけない
2 設備投資のタイミングを再計画しなくてはいけない。設備投資を抑えていくのか、このタイミングで設備投資をすることで、人件費の見直しをする必要がある
3 具体的な受注量がどのくらい減った場合に、資金がいくら必要となるのか、メイン銀行に頼むのか、国民政策金融公庫などの特別融資などを使えるのか、金利はいくらぐらいとなるのか、様々な予測データを算出する
仮にですが、これらを企業の経理部または経営企画部あたりが算出するとなると、どのくらいの時間と人員が必要となるでしょうか?
私は、このような試算をしたことはないのですが、大企業や中堅企業であれば、いままで専任の方がいくつものシミュレーションをしてきたことかと思います。
しかし、DXができている中小企業であれば、
「トランプさんが関税増加をします。日本経済へのダメージと、弊社は大手〇〇社からの受注が30%あるため、どのくらいの減少になるかシミュレーションしてください。そして、必要資金と資金調達、それら以外に必要と思われる対策を10個ほどアイデア出ししてください」
こんな文章を1分でいれれば、AIが3分もしないで返答してくれるのではないでしょうか?
そして出た回答を元に、幹部会議にかける、メイン銀行へアポイントをとって融資相談をするなど、アクションに起こすことができます。
いままで情報収集と分析に1週間(相当な熟練者)で行っていたことが、4分程度で行えて、すぐにアクションにうつせることができると思います。
経理担当者である私にとっては、これがデジタル化による恩恵で、経理の仕事が改革されると思います。
社内のデジタライゼーションに、毎月の試算表や、自社の変動費や粗利率、借入金一覧表などを読み込ませていれば、売上の減少が10%きれば、いくらの運転資金調達が必要などのアラートがでる、期末までの下降修正の予算書ができあがるなども行われるでしょう。(すでに会計ソフトによっては、このような機能は搭載されているかもしれませんね)
Xとは、今までの常識を破壊して、生き方を変えることでは?!
Dを手段として、Xを目的として考えてきました。
でも、やはりXそのものも手段にすぎないのかと思います。
では、目的は何か?
今の段階で、明確な目的というものの模範解答を示すことよりかは、常に「模範解答はなんだろう?日本にとって、会社にとって、自分にとっての模範解答は?」と問いかけて、考えて、行動することに価値があるように思います。
私淑している文筆家の千田琢哉さんから、
「人の半分の時間で、倍の成果をあげられることは何か?それが、あなたの才能であり、得意技だ」と学ばせてもらいました。
まさに、Xの本質そのものかと思います。
「労働時間を8時間から4時間に減らして、売上をいまの倍にする」これができたら、トランスフォーメーションができたといっても過言ではありません。
50%の改善では、まだ”今の延長線”。でも、51%を超えたとき、”未来の入口”が開く
改革は51%と記載しました。
労働時間を8時間から4時間に減らして、売上をいまと同じに維持できたら、50%の業務改善ができたと言えます。
でも、50%の改善であって、51%の改善にはいたりません。
実は、僕はこのロジックに悩み、1%ってどういう意味だろうか考えました。
その中で自分の解釈は、
「1%を超える」ということが、社会の、自分の限界を超える「際」なのではないかと感じました。
限界という表現だったり、常識だったりするものです。
もし、2029年のある日、出社すると、
「AIエージェントが仕事まきとってくれたから、明日から8時間働かなくていいよ。4時間でいい。もちろん給料変わらないから安心して」
と上司から言われたら何をしますか?
1日4時間が浮いたら、勉強したり、新商品開発したり、家族と遊んだりできるでしょう。
私は、家でNetflix・Hulu・Amazonプライムを観まくります。そして、トレーニング行ったり。あと、大学院にも挑戦したい・・・と4時間が足りなくなるくらいになるでしょう。
そして、2032年のある日、出社すると、
「いままでどおり、4時間は働いて欲しい。でも給料は倍にするから。みんなとAIエージェントのお陰で、売上倍になったからさ」
と上司から言われたら何をしますか?
海外旅行に行ったり、家を買ったり、車を買ったりできるでしょう。
私は、「給料は一緒でいいから、2時間労働にしてください」って言いそうです。
そんな未来がきたら、時間の絶対的価値はかなり高まっているような気がするからです。
Xを実現している未来って、いまの仕事・業務・ビジネスの延長線上にないんだと思います。
働き方・人間関係・構造・時間の価値・生き方、すなわち常識がガラリと変わることでしょう。
哲学そのものが変わるといってもいいくらいです。
これが、トランスフォーメーションをする、Xの実現と思っています。
DXのXをするために今からできること
DとXを分けて考えました。
私は、労働時間が半分になったら何をするのか?を常に言語化しつつ、それを目的として、日々デジタ化に勤しみたいと思いました。
人が行うことは間違えが発生します。デジタ化になって、そのような間違えがかなり減るようになりました。常日頃、「もっと楽にできないかな」「もっと人の工数を減らせないかな」「浮いた時間で、本読みたいな」など、怠け心にはどめをかけないことが、デジタ化・合理化・効率化の哲学的なマインドです。
これは、真似をおすすめしませんが、私がITリテラシーを高めようとした、高め続けてこれたモチベーションが、「積極的に怠けるための努力をしよう」と不純な動機で生きてきたからだと思います。
遠い将来ではなく、近い将来にXを実現した、現実がやってきます。
その日に向けて、粛々と準備をしましょう。