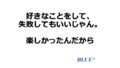先日、広島県出身の現役隊員さんが私のnoteにスキをつけてくださいました。広島と聞くとOV会会長を思い出したので記事にしてみました。
協力隊での出会いって不思議だと痛感した時
2025年6月に、全国協力隊OV会に出席しました。正確に言うと、JOCA(公社)青年海外協力協会の評議員会です。この評議員会にOV会々長は任命されます。また、OV会以外にも任国会の役員もいらっしゃいます。便宜上、全国会と表記しますが、ここでの出会いって訓練所のような驚きと学びがありました
この全国会には50名近く出席していたと思います。九州からは私を含めた2名だけでした。
派遣前訓練所は、全世界に同時に派遣される同期です。
それに対して、OV会などは、派遣時期も任国も職種も違うけど、同じ地域に住んでいる、または同じ地域と縁のある人の集まりです。
つまり、世代を超えた青年海外協力隊の集まりです。
訓練所は3ヶ月あるので、ある程度まんべんなく話せますが、全国会は半日です。13時半から開始して、懇親会は19時終了。そのあと宿舎で2次会があります。限られた時間で色々な方とお話したいと思っていました。
そんな時に、総会でしっかりと意見を伝えていたのが、広島県OV会々長でした。想いがまっすぐで面白そうな人という印象を受けました。
そして、自分と真逆の意見。
でも、「青年海外協力隊が好きなんだ!!」というベクトルが同じことは匂いから伝わって、ワクワクがとまりません。
100人と1分ずつ話すか、1人と100分話すか。
過去、色々な会合をでて、全員と1分ずつ話して名刺交換したことがあります。帰宅して思うことは、全員の顔と名前が一致しないのです。何か虚しくなりました。
それらのこともあり、会合では1人としっかり話し込んで帰る、マイルールをつくりました。
今回の全国会では、宿泊施設での2次会において広島県の会長さんと100分くらいお話することができました。
何を話していたのか?と言われると、協力隊OV会のこと、協力隊のあり方、自分の仕事やプライベートなど多岐に渡りました。
特に協力隊については、私と真逆の考え方でした。
意見が真逆すぎて興味をもったから当然です。
この真逆の意見を持つ集まりに、私は訓練所生活を彷彿していました。
お互い自分の意見は言い合うものの、決してその価値観を押し付けることなく議論できることは非常に楽しいです。
きっと、お互いのベースに敬意があるからです。敬意がなくなると、喧嘩になるので周りがひいちゃいます。
私は、100分近く1対1で対話できたので実りある会合となりました。満足して、就寝。
広島県の会長さんは、ベテランなこともあり、また別の人とお話しに行かれていました。
OV会の課題ってなんだろう?
個の集団
OV会の課題、帰国した後の協力隊の課題、社会還元の課題、ってなんだろうという議論もでました。
1つは、OV会の発言権って弱いよね、ってことでした。青年海外協力隊が帰国後かかわる関係機関というのは、主にJICAとJOCAです。
誤解しないでもらいたいのは、JICAとJOCAに聞く耳がないということではありません。
各県で活躍するOV会の意見を集約する場がないので、全国OV会としてのまとまった意見を持ちづらいということです。
まとまった意見を持ちづらいと、影響力が小さくなります。
そこが課題じゃないかと。
ただ、ある意味そのような全国OV会のようなものがないのも青年海外協力隊らしいといえば、らしいです。
理由は、海外で一人暮らしをできちゃう青年海外協力隊は、連携や協力はしても組織化に向いていない気がするからです。
「孤独をこよなく愛する個の集団」というのが私の印象です。プロジェクト単位であれば、一気に集まって協力しあう。
終了すれば、サクッと解散。
「君子の交わりは淡きこと水の如し」そんな表現が合うし、そうでありたいのかなと、勝手に思っています。
なので、全国OV会というのが今までもなく、これからもないのかな?と思ます。私も、「みんなで作ろうよ!」とは思えないのが正直なところです。
無関心
もうひとつ、別の課題は、無関心だと思います。
協力隊経験は2年間です。そして、帰国した後の人生は何十年と続きます。
つまり、途上国の活動以上に、帰国してからの活動時間が圧倒的に長いのです。
OV会は帰国した後の隊員が、各地域で活動するためのコミュニティです。
私は、組織論でいうところの、20:80の法則、パレートが好きです。
そのため、その法則で考察してみます。
20%の人が、80%に影響を与えているという法則です。
もしOV会でいうなら、OV会の運営と出席者が、帰国者の20%の人数で、80%の影響や貢献をしていることになります。
一見すると意見が違う、対立する場合は違うグループと思われます。
でも、Aという意見とBという意見をもっているというのを一緒のグループにすると、そうではないグループは無関心のグループです。
帰国後、OV会などに参加せず、ご自身のことだけをしている人たちもいます。私はこのような人たちを否定するつもりはありません。
義務もありませんから。
個人の選択ですので尊重しています。
OV会は、帰国して協力隊関連から離れている人たちに少しずつ届くアクションをしたり、細く長いつながりを持てたらいいなと思うところです。
広島県の会長と話して意見が違うけど、「青年海外協力隊が好きだ」ということだけは一致し、肌感覚で伝わってきたことです。
10代から30代の関心がある層をどう巻き込むか
もう一つの課題が、10代から30代の関心がある層をどう巻き込むかです。もしかしたら、JICAの仕事かもしれませんが、興味があることには首をツッコミたくなるコミュニティ開発(村落開発)の特性です。
2025年度の宮崎県OV会で、青年海外協力隊に興味がある大学生が遊びに来てくれました。OV会で活躍する先輩が、別のイベントでの出会いをきっかけに招待してくれました。
総会で10代20代とお話する機会があったのですが、情報収集はすべてネットで行っていることがわかりました。協力隊関連の情報は、SNSやオンラインで参加していました。
それらのことから、特定のイベントだけではなく、日常で協力隊関連にアクセスできる場所があると、非常にインパクトをだせるのかと思いました。例えば協力隊チャットボットを作成すれば、知りたい情報や悩み・相談を24時間365日対応できます。
そして、それらの質問内容が情報となって発信方法も修正していくこともできます。
AIを活用すればできると思います。
この発想は、ブロードリスニングという手法です。
東京都の政治に対する意見を誰もが言いやすいように窓口をつくり、それらの情報を数時間でデータ処理しました。
それにより、10代から30代の声を拾い上げることに成功し、若者支援の長期戦略化が政策の柱にの1つになった事例となっています。
東京都知事選に出馬し、新党チームみらいの党首安野貴博さんの著書から学びました。(「はじめる力」安野貴博氏著)
結論
帰国後の課題感は3つです。
1 OV会としてまとまった意見を集約する必要はあるのか無いのか
2 無関心層にどのようにアプローチしていくか
3 10代から30代の関心がある層をどう巻き込むか
無関心層について補足させてください。
無関心層というとネガティブに聞こえるので、OV会に参加していない、という定義です。
「帰国してから何もしてなくて・・・」とおっしゃる人と会うのですが、その人がまったく協力隊経験を活かしていないかとイコールにはならないと思います。
その人の日常での言動が職場やコミュニティに影響を与えているのであれば、十二分なご活躍です。
現に、協力隊出身のユーチューバーの方もいらっしゃいます。
私が言いたいのは、OV会に参加して欲しいというよりか、つながりを持たせてもらいたいということです。
いや、でもそのユーチューバーさんとメールしたことがあるのですが、何か企画を出せばのっかってくれるような気がしますので、無関心層という言葉が良くないのかと思いました。
個の力が強い協力隊ですから、ベタベタするような集まりは提案するつもりはないのですが、つかず離れずでつながりあうことで、面白いことしたいです。10代から30代の協力隊の卵へ一緒にアプローチしたいです。
書いてて、2と3は別々の課題感と思っていたのですが、組み合わせできそうですね。
帰国後、色々なフィールドで活躍するOV会と離れている人たちと、10代から30代の協力隊の卵の方たちをつなぐことができれば、良い影響力が生まれそうな・・・
結論と題したのに、また新たな問いかけが生まれました。
この着眼点からまた、色々模索してみたいと思います。
思考のプロセスでの発言となりましたが、常に試行錯誤していることを共有できたら幸いです。
帰国後、どのようなテーマをもって活動したいですか?